思考の変遷 130405
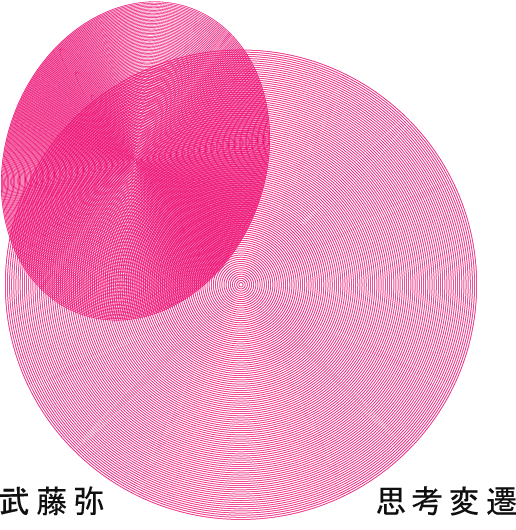
2010年の夏ぐらいだった。リーマンショックの影響がまだ色濃く残っていて、景気が落ち込んでいるところに、震災があり、世はなんとなく暗く停滞感を持っていた。いくつかのシェアハウスやシェアオフィスの事業を行っていた我々に、ある方のご紹介で上馬のお屋敷の物件の相談が来た。それがThe Forumとなって再生した案件だ。すべての不動産は世界に一つしかないし、固有性を持っている。しかし、その固有性が、ここまで際立っている案件は奇跡的だった。
まず所有者。かの著名な経営学者野田一夫先生がかつてご自宅に使っていた。もともとは米系の製薬会社の日本代表が50年前くらいに建てた。日本建築好きの外国人で、モジュールとかは日本のそれではないが、使っている素材は日本のモノ。見事な和洋折衷のお屋敷をつくった。それを野田先生のお父様が気にいって買ったらしい。ちなみに野田先生の息子さんは、これまた力のある、ウェディング運営会社プランドゥーシーの野田豊さん。羽沢ガーデンとか素晴らしい施設を運営してきた人だ。野田豊さんの美意識の原点が、この上馬の家にあるとのこと。確かに、建物と庭の関係や、植物、池の関係など、プランドゥーシープロデュースの案件に通ずるものがある。子供のころからこんな風景見て育ったことは、すごく財産なのだろうなと思う。
野田先生はかつて、Forumというビジネスパースンのコミュニティーを運営していた。昭和50年代に、紀尾井町にて行っていたらしい。会員制クラブがあり、スポーツジムがあり、共用の会議室があり、小型の事務所、そして、キャレルという席型のシェアオフィス。まさに、そんな時代から新たな働き方を提唱し、実践してきた人だ。
次にタイミング。これが、景気がよく、高給取りの外国人エキスパッドが多くいるタイミングだったら、僕らにこの案件の相談はなかった。普通に月200万とか支払う投資銀行の人とかが住んだだろう。リーマンショック後、多くの外資投資銀行が日本の人員を減らして、アジアの拠点から日本をはずし、香港とかシンガポールとかに移っていった。そこに震災が追い打ちをかけた。そのタイミングだったから、この建物も運用方法に窮していたのである。
不景気という環境が我々にはよいタイミングだったこと、所有者の方が持っている物語、そして建物の力、それらが絶妙に組み合わさって、シェアオフィスThe Forumは出来上がったのだ。
思考の変遷 130402
2013.4.2 WATARU MUTO
不動産、建築と、金融は切っても切れない関係だ。
シェアハウスなどまだ投資商品として十分に認知されてない物件を作り、開発していると、いつも金融の壁にぶち当たる。リノベーションもまた然り。
つまり金融機関が評価できないのだ。結果、資産の流動性が普通のモノに比べ低くなる。アセットタイプによるものもあるが、例えば、新築と中古だと流動性はかなり変わる。
例えば、税務上の残存期間しかローンのアモチ期間を見られない場合が多い。すると、古い物件はそもそも融資対象となりにくい。人々の暮らしや、都市景観を変えていこうとするのであれば、金融の仕組み、解釈を変えていくという作業が必須だが。
金融庁と国交省のパワーバランスの問題でもあるのだろうな。やはりより優秀(学歴という意味で)な人がいる省庁の方が強いんだろうな。
昔聞いた話で、サブプライム問題はなぜ起きたかというはなし。
ハーバードとかの優秀な人たちの中で、最も優秀な部類の人たちは、自分で起業する。
その次ぐらいの人たちが投資銀行に就職していく。そして真ん中ぐらいの普通の人たちが、格付け会社に就職していく。
つまり、自分より頭のいい人たちが作った、金融商品など評価ができないのだ。
その金融商品を作った人に、評価の仕方を教わったりして、AAAとかいう評価をつけているわけだ。それはやりたい放題だろうなと思う。
日銀がどんなに金融緩和と言っても、要は、金融庁が、不良債権起きたときに結局レンダーに責任とらせますよ、という態度でいる限り、銀行の姿勢は簡単には変わらないだろう。
そして、わかりやすい方向のみに資金が集中し、局所的な一時的資産インフレが起きる。そっちの方が危ないとわかっていても。
税務上の残存期間しかローン元本返済期間を見られないという形である限り、古い建物はなかなか流動性を確保できず、結局、壊して建て直したほうがいい、という従来の流れになる。
いったいそれにより、どれだけの社会資本を毀損したことか。
誰の意思が働いてそのような制度設計になっているのか。日本人を疲弊させて貧乏にさせることにより誰が得をするのか。
穴を掘って、その土で、隣の穴を埋めて。また掘って、また埋めて。
壊しては建て直し、又壊し
思考の変遷 130401
2013.4.1 WATARU MUTO
僕のビジネスの先生は、リクルートを創業された江副さんだった。
2001年に建築の大学院を卒業した。その時は、いわゆる不況就職氷河期で、僕の研究室の先生はそれでも、力のあった人なので、同窓生は、竹中とか大成とかそこそこのゼネコンに就職したり、三井不動産とか、しっかりした会社に入っていた。
僕はそのころ、ほっといたら模型を作ってしまうような、超デザイン意匠思考の人間だったので、著名巨人建築家のアトリエを紹介してもらって、1週間くらい働いたりした。
でも何かしっくりこなかった。
建築を作るということをもっと、お金の流れとかそこから考えないと、建築家という職能自体が立ち行かなくなるのでは、と、思った。
その時に江副さんに誘われて、江副さんがリクルート等の一線から離れた後にやっていた会社に入れてもらった。ディベロッパーだった。
江副さんはディベロッパーアーキテクトという言葉を教えてくれて、僕らにいろんな機会を与えてくれて、多くの体験をさせてくれた。
僕の考え方の中心はその時に教わった考え方が基本にある。
今年、そんな江副さんが亡くなられた。
江副さんには、最初っから、結構高額の給料をいただき、何もできない僕にいろんな機会を与えてもらった。投資していただいた分、儲けていただく前に、僕は会社を辞めてしまい、リノベーションの会社などを作って今までやってきた。
辞める際に、世話になった分をお返しできてないと思っていたので、とりあえずその当時自分がかかわっているプロジェクトが着地するまでは、無償でもよいから、最後まで見させていただきたい、と、進言したら。江副さんは、中途半端はよくない。君は君が次にすべきことに全力になりなさい。と、言ってくれた。そして、僕がやろうとしているリノベーションプロジェクトの話を聞いてくれて、投資規模感含めてちょうどよいね、と言ってくれた。そして僕はすっきりやめて、次の事業に打ち込めた。
辞めた後も、もう少し自分でしっかりした事業をつくり、胸をはってご報告に行き、場合によっては、物件ベースでもよいので投資をしていただき、儲けてもらう。ということをしたかったが。
そんな当時のメンバーと江副さんを偲ぶ会を先日行った。
皆元気だ。活躍している。
東京R不動産もそうだし、candeoホテルもそうだし、visixや。外資投資ファンドで稼いでいる人もいるし。みな、当時、切磋琢磨したメンバーだし、不動産、建築業界に少なからずの影響を与えている人たちだ。
江副さんのヴィジョンの旗印に集まった人間が、今では、散り散りなったが、それぞれの立場で活躍している。
江副さんに経済的恩返しはできなかったし、大金持ちだから、たとえ少しリターンを出せたとしても、さしたる影響はなかっただろうが。
何か、学んだものを、基礎としながら、しっかりと事業を作っていきたいとあらためて思った。
シェアハウスはしっかりやれば、しっかりした市場を形成できるし、やってそうでちゃんとやられていない。そして、人々の暮らしにしっかりとした価値提供ができるはずである。そういう暮らしを事業を通して提供すること。それのみだ。
江副さん、改めて、ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。
